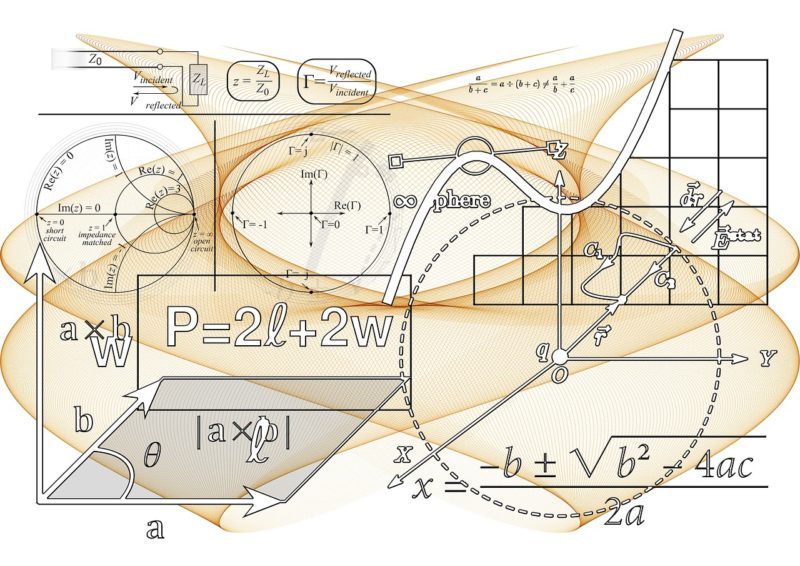中学受験のカリキュラムとしては少しゆっくりめかもしれませんが、小学5年生の算数がつるかめ算に入りました。
つるとかめの合計数がわかっていて、そこからそれぞれの頭数を求めるアレです。
中学生で習う連立方程式の問題を、方程式の概念無しで解くわけですから、中学受験の難しさを象徴する問題として長く君臨していた問題です。
ここで「君臨していた」と、過去形の表現を使ったのは、現在の中学受験の世界では、つるかめ算は決して難問ではなく、むしろ基本問題として扱われているからです。
中学受験算数の中でのつるかめ算の位置づけが低下したのは、たぶんに「面積図」を使った解き方が普及したからではないかと思います。
私が塾でつるかめ算を習ったのは、私が小学5年生の時、つまり1983年のことです。(塾生には、私は18歳ということになっていますので、これは秘密にしておいてくださいね)
その時のことは今でも鮮明に覚えています。
なぜなら、その時、つるかめ算は授業最後のチャレンジ問題として出題され、
「興味がある子だけ居残って解いてみなさい」
という指導も何もない中で、
「なるほど、脚の差が集まって、現実と仮定の差が生まれると考えるんだな。」
と、解き方を自力で見つけ出せた感動がとても大きかったからです。
逆に言えば、当時の塾では、つるかめ算を明確な決まったやり方で解く方法を授業で教えていなかったということになります。
そもそも、「面積図」という考え方を教わった記憶がまったくありません。
興味深い記事を見つけました。

この記事の中に、
私は、1980年代に塾の講師になったときに、はじめて面積図を知り
とあることから、当時はまだ面積図が必ずしもポピュラーなものではなかったことが推測できます。
以前、速さの公式を覚えさせるのに「みはじ」「きはじ」という方法論があることをこのブログで書きました。これも、やはり1980年代には、まだポピュラーではなかった方法論です。

つまり、「教え方」というのも、現在も日々進化し続けているということなんですよね。
それがまた、この仕事の面白さであり、いつまでたっても「まだまだ」だなと感じざるを得ない大変さだったりします。
大人になってからも勉強・・・いえ、勉強できる大人になるために、子どもたちには勉強に親しんでほしいと思います。
それでは、今日はこのへんで。